
vol.5 2025.3.31
西塔大海(SML編集長)× 來島政史(面白法人カヤック・スマウトディレクター)
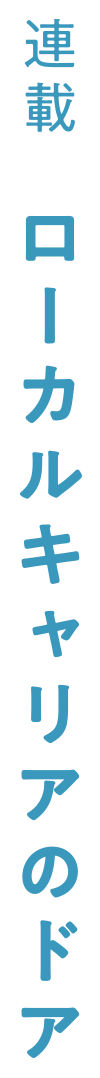
SML編集長の西塔です。 この特別対談では、地域おこし協力隊の先に広がる、あまり知られることのないローカルキャリアの世界を、皆さんにご紹介していきます。
今回のゲストは、鎌倉に本社を置くIT企業「面白法人カヤック」の、ちいき資本主義(まちづくり)事業部で地域プラットフォーム「スマウト」やコミュニティ通貨アプリ「まちのコイン」のディレクターを担当する來島政史(きじま・まさし)さんです。
プライベートでは、來島さんの地元である逗子での日常や人の繋がりを記録するローカルメディア「ズシレコラジオ」を立ち上げ、200回以上もポッドキャスト配信を行っています。また、逗子で行われている「池子の森の音楽祭」の実行委員として地域のイベントにも関わるなど、多彩な顔を持つ方です。
そんな來島さんと、都会と地域をまたがった働き方、ライスワーク(仕事)とライフワーク(やりたいこと)の融合、そしてその先の未来について、お話を伺いました。地域おこし協力隊員の皆さんはもちろん、これからローカルキャリアを目指す方、仕事とやりたいことをどうつなげていくのかに迷っている皆さんにも、新しいヒントになるエッセンスが盛り込まれているのではないでしょうか? 早速お話を伺いたいと思います。

一体何者なのかわからない幅の広さ
西塔編集長(以下、西塔) 來島さんとは「面白法人カヤック」(以下、カヤック)が受託している地域おこし協力隊の戦略的広報事業などでお会いする機会をいただいていますが、改めて來島さんが何をしているのかを教えてください。
來島さん(以下、來島) そうですね。西塔さんとはお仕事でもご一緒していますが、改めてお話ししますね。
僕は鎌倉にあるカヤックの、ちいき資本主義事業部で働いています。カヤックは面白いコンテンツを生み出すことを軸にゲーム制作や広告企画、地域通貨、関係人口促進など、とにかくいろんな事業をやっている会社で、ぼくは2007年の入社当時はインタラクティブなWEBサイトを作るFlashエンジニアをやっていました。Flashサイトとかが全盛期だったころですね。
そのあとはゲームプランナー&サウンドディレクターを経て、今の地域に根ざした事業を展開する「ちいき資本主義事業部」に移り、コミュニティ通貨アプリの「まちのコイン」の開発や運用に携わり、現在は地域プラットフォーム「スマウト」のディレクターをしています。
ほかにもプライベートでは地元の神奈川県逗子市で野外フェスティバルの企画運営をしたり、趣味や複業としてポッドキャストや地元のコミュニティFM でラジオパーソナリティーなんかもしています。
一体何者なのかわからないかもしれませんが、今は、ライスワークとしては地方創生、移住関係人口や地域おこし協力隊の制度のPRや制度支援などをさせていただいています。
西塔 幅が広い! WEBやゲームから今の地方創生や関係人口といったローカルな仕事に移ったのはご自身の希望だったんですか?
來島 はい。WEBデザインからゲームクリエイター、そしてローカルへと、ある意味では全然関係ない分野へと移っていったので、社内転職するような感覚ですね。カヤックは本当に事業の幅が広くて、面白法人という名前の通り「人を夢中にさせるものを作る」というクリエイターマインドを強く持っています。僕はこのマインドが好きで、自分自身でもその時々に興味がある分野や、事業部が立ち上がったタイミングで手を挙げて、クリエイターとしてできることを模索してきました。
地域のミクロな活動に根差すからこそ
西塔 何かきっかけはあったんですか?
來島 これまた異なる分野なのですが、実は昔から音楽が好きで、10代はそれこそバンド活動に傾倒していました。20歳のころには地元の小さなイベントでボランティアスタッフとしてステージの音響など裏方として関わっていました。有志で「心地いい空間を作ろう」という雰囲気がとてもよくて、こんなふうに町に対して自分が好きなことや、いいなと思ったものを発表したり紹介する場をつくるのがめちゃくちゃおもしろいなって思ったんです。
その後、30代で地元の逗子に戻ってきて、家を建てて「ここで暮らしていくぞ」って決めたときに、「地域に対して何か自分にできることはないかな?」と考え始めました。都内で暮らしている間は薄れていた「地元で面白いことを立ち上げたいな」っていう感覚が戻ってきました。
2019年に「まちのコイン」というコミュニティ通貨アプリをカヤックが立ち上げたのですが、地域の面白い人たちやその取り組みをアプリで可視化するその仕組みが面白いなと思い、いまの事業部への異動願いを出しました。ゲームって人を夢中にさせるノウハウの塊なので、ゲームクリエイターとして、それを地域にうまく転用できないかなって思ったんです。
西塔 ゲーム、音楽、ローカルという3つの川が合流していったんですね。これまでやってきたプライベートの活動と自分のリアルな仕事がくっついたわけですが、それって、仕事の手応えとしてはどうだったのですか?
來島 そうですね。元々は、イベントのボランティアがスタートだったので、ローカルなものをビジネスにしようとか、マネタイズを考えるっていうよりも、本当に趣味の延長線上で逗子や鎌倉といった特定の地域をミクロな視点で捉えていました。
そんな20代から30代前半までを経て、今までは逗子、鎌倉というミクロだった視点が「まちのコイン」や「スマウト」という全国的なプラットフォームを通じてマクロに変わっていきました。自分の中で解像度が変わってきたんだと思います。ミクロとマクロを行き来できることは、「スマウト」チームや社内でもレアだとよくいわれますね。
西塔 本当にその通りですね。來島さんのいろんなお話や考え方にいつも説得力を感じていたんですが、それは地域のミクロな活動に根差しているからなんですね。納得です。
音楽を通じて見えた「楽しいものを作る」効果
西塔 ミクロの視点での逗子や鎌倉でのお話をもっと掘り下げたいと思います。逗子では具体的にどんな活動をされているんですか?
來島 逗子では「池子の森の音楽祭」という野外音楽フェスティバルの企画と運営に5年くらい関わっています。
「地元の逗子で音楽イベントを」という思いに至るまで、ある原体験があります。夏のシーズンの逗子海岸に「海の家+ライブハウス」というこれまでになかったスタイルの施設ができて、全国的にも話題になった時期がありました。
この立ち上げや運営に当時少し関わっていたんですが、それ以降に似たようなスタイルの海の家が増えた結果、騒音や治安の問題も出てきてしまいました。そうなると、「逗子で音楽イベント」という組み合わせにはネガティブなイメージがついているように感じてしまって。それをなんとかポジティブな方向に転換していきたいと思って、「池子の森の音楽祭」に積極的に関わるようになりました。
西塔 なるほど。音楽に限らず、新しい取り組みにはどうしてもつきまとう問題ですよね。 一方の「池子の森の音楽祭」はどんな内容なのですか?
來島 「池子の森の音楽祭」は、逗子在住の子育て中のパパママ世代が中心に運営していて、スチャダラパーさんやアン・サリーさんなどのメジャーなアーティストも出演してくれています。
そこで僕自身は、子どもが楽器を自由に触れる「ミュージックフィールド」というブースを手掛けています。学校の音楽室にないような、普段大人が「これは触っちゃダメだよ」っていうような楽器も含めて、「自由に触っていいよ」っていうブースです。 シンセサイザーやエレキギター、エレキベース、あとDJのターンテーブルなどをダーッと並べて、「自由に触っていいよ」っていう。それが毎年好評なんですよ。
実は9割以上が僕の私物なのですが、毎年来てくれている子がドラムがうまくなっていたり、「ギター始めました」という子がいたりするんです。「もしかしたら音楽に対してポジティブな影響を出せているのかも」と感じています。
西塔 それは素敵ですね! 教室ではなく「自由に触っていいよ」から始まる音楽とのコミュニケーションですし、これは行政が予算取ってできる話じゃないですもんね。
來島 割と町の外れでやっているので、ステージではいわゆる野外フェスと同じくらいの音量で楽しめます。騒音の問題については、ちゃんと近隣の方々に紹介や説明をして回ることを大切にしています。誰しもそうだと思うんですけど、自分の知らないところで起きている話はやっぱり気になるし、ネガティブな感情も抱きやすくなりますからね。
西塔 すごく大切なことですし、そういうことをされている方ってそんなに多くないんじゃないかと思います! 楽しいものを作る、人を夢中にさせる仕組みを作る一方で、配慮や経験もされているのが來島さんの面白さであり、深さですね。
社会資本や環境資本を可視化する
西塔 先日拝見させていただいた、カヤックのオフィスもものすごく面白かったです。
まち全体をオフィスと見立てて、昔からあるビルや古民家などいろんな形態のオフィスが点在していたり、一般の方も入れる「まちの社員食堂」があったり。さらには商店街の理事会にも加わっていることをお聞きしました。スタートアップのIT企業ではなかなかやれないし、わざわざやらないことだとも思います。
そんな役割をあえて担っているという來島さんの所属する「ちいき資本主義事業部」では、どんなことをされているのですか?
來島 「ちいき資本主義事業部」は、カヤックが提唱する「地域資本主義」という考え方をベースに事業を展開しています。この「地域資本主義」とは、地域は「経済資本」「社会資本」「環境資本」の3つの資本で捉えるという考え方です。「経済資本」は、既存のお金や物質的な資本を大切にして、しっかり稼ぐこと。「社会資本」は、いわゆる人と人とのつながりです。そして「環境資本」は、自然や観光資源などのこと。カヤックが大事にしているのは、目に見える「経済資本」と、目に見えない「社会資本」、「環境資本」という3つをしっかり伸ばしていくことです。
とはいえ、「社会資本」や「環境資本」は見えづらい。これを可視化できれば、それぞれの地域の個性があぶり出されてより面白くなっていく。そのためのプラットフォームや事業を担っているのが、ちいき資本主義事業部です。
西塔 なるほど。地域のウェットな人間関係とデジタルの世界って今までは水と油の関係だと思われていましたよね。その2つを組み合わせることに、現時点で手応えはありますか?
來島 手応えは感じていますが、一筋縄ではいかないのもまた正直なところです。
プラットフォームの一つである「スマウト」では、地域に関心のある人材と地域とのマッチングを行っています。ここでつながった人同士のコミュニケーションを通じて、地域ごとの特性が見えるようになってきています。
また、コミュニティ通貨アプリ「まちのコイン」は、熱狂的に活用してくださっている方もいる一方で、広がりにはまだまだ課題もありますね。
実験的に始めて、とにかく継続すること
西塔 地域とつながるプラットフォーム「スマウト」は、移住希望者と地域のマッチングを促し、年齢を問わない多くの人材がローカルに飛びこむ仕掛けになっています。また、來島さん自身もローカルを大切にしつつ、全国の地域と関わることがビジネスになっています。こういう仕事ならではの面白さややりがいはありますか?
來島 やはり、ミクロとマクロの視点を行き来できるのが面白さだと思います。地域プレイヤーの悩みや課題感を共有するミクロと、プラットフォームを利用していただく一般ユーザーさんの気持ちもわかるマクロの両方の視点が得られる。
たとえば、地域おこし協力隊に興味を持つ方は20代から50、60代以上まで本当に幅広いんですよ。 その中で自分の経験や特技を活かして地域おこし協力隊として活動したいという方もいらっしゃいますし、一方で地域側にも求めていることはあります。それだけに、まずは「聞く」姿勢が大事なんですよね。
西塔 聞く姿勢って本当に大事ですよね。実際に、先にやりたいことをやらせてもらったとしても、うまくいくことばっかりじゃないですしね。來島さんをはじめ「スマウト」事業のスタッフの皆さんに失敗も含めた経験があるからこそ、「スマウト」は移住希望者と地域を結ぶプラットフォームとして成り立っているんだなと感じます。
來島さんの仕事ってとても面白いですよね。でも、ビジネスとしては直結しにくいところもある。何をスキルとして磨いたり、経験として得たりするとそんな仕事ができるようになるんでしょうか。
來島 ゲームクリエイターしかり、「スマウト」しかりなのですが、僕は実験的な取り組みを継続してみる感覚があって、それが身を結んでいるのではないかと思います。最近それを感じたのがポッドキャストです。
地元の逗子・葉山エリアを紹介する「ズシレコラジオ」というポッドキャスト番組を、2019年から現在までに200回ぐらい配信をしています。いわゆるローカルメディアをやりたいなと思ったのがきっかけで、ポッドキャスト以外にもいろんな選択肢がある中で、音楽をやっていたので録音技術があったり機材も持っていたりして特技を活かせると思えたことから始めました。
西塔 なるほど。実験的に始めやすいってすごく大事だと思いますが、継続できるかどうかについてはどうお考えですか?
來島 そうですね。1つの街について200回も情報発信をするって、ちゃんと町を見ていないとできないことだと思います。新しいことを始める人もいれば、移住者もいる。
西塔 それはカヤックさんのサービス開発にも通じるものがありますよね。自分の好きなこと、できることをまずは実験的に始めて継続するうちに、誰かが見つけてくれて仕事になっていく要素があると。
來島 合気道みたいですね。相手がこう出た!ということに対して、それを生かしてテコの原理で別の力に変えていくわけです。
リーダーシップだけではない地域でのありかた
西塔 僕が來島さんに親近感を抱く理由がわかりました。まちづくりの仕事をしたいと思った時に、リーダーにならないといけないって思い込んでる方がとても多いと思うんですよ。その部分が來島さんのおかげで言語化されました。
來島 誰かがやりたいと言ったことをどうやって形にしていくか。会社の中で仕事をしながらやった方が、それこそこう、なんでしょうか。 筋はちゃんと通しつつ、面白いことをやりたい人と一緒にやりたいことやっていくっていうことが、社内でも社外でもやりやすい環境なわけですよね。
西塔 私もそう思います。地域おこし協力隊の方の中にも、リーダーに向いてる人とフォロワーシップを発揮した方がいい人がいるなと思うんですね。
來島さんはフォロワーシップをうまく発揮しながら、じわじわと会社の中でも外でも仕事を作っている。趣味だか仕事だかわからないけれどやりたいことがたくさん出てきている中で、大切にしてる軸はありますか?
來島 逗子に家を構えて、ここで暮らしていくことを決めたときに、同じ住むなら町が面白くなったほうがいいし、自分の人生そのものも面白くなるだろうって気づいたんですよ。逗子や鎌倉、葉山というところは、思いのほか不便なんです。ただ、自然がいいよねとか、海が近くていいよね、というように不便を上回る何かしらの恩恵が得られる場所に住むと決めて移住してくる人たちとは、価値観がめちゃめちゃ合うんですよね。
例えばネットで間取りや家賃を比較して家を決めるときの感覚と同じで、条件で自分の住む町を決めると、町に対して受け身になる傾向があると感じます。この町の自治体は、どんなメリットを与えてくれるんだろう、という。一方で、自分からこの町をちょっと面白くしてやろうとか、週末にイベントをやって町の人と盛り上がろうなどと、能動的に自分からコミットしようという感覚になれると、結果的には自分の住む町は面白くなるし、ひいては自分の人生も面白くなると思うんです。
僕はプライベートと仕事を行き来しながら、そんなことを思ってくれる人を増やしたいし、やりたいことなんだなって思っていますね。
西塔 とても面白くお話を聞かせていただきました。逗子に深く深く根を下ろしていけばいくほど、それと同じ体積の分だけ、「スマウト」などのカヤックとしてのサービスを使って外側に広がる仕事もあるし、キャリアも作れて、その先には未来を作っていけるんだなっていうことを感じました。ありがとうございました。
(参考URL)
・コミュニティ通貨アプリ「まちのコイン」
・地域とつながるプラットフォーム「スマウト」