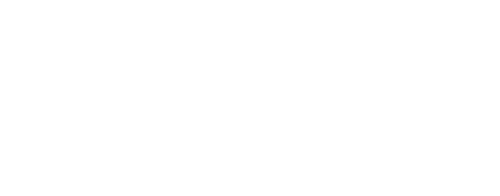
2024
PROJECT08 | 市民活動と人 隊員活動レポート

野見山茂さん(以下、野見山さん)のミッションは、“人と人”、“人と組織”をつなぐことで社会課題の解決を目指すことです。NPO法人さが市民活動サポートセンターと連携したCSO連携型地域おこし協力隊「さがむすび隊」として、「防災」「こども」「まちづくり」に関する課題と向き合ってきました。3年目はたくさんの縁が繋がり、自走のビジョンが見えてきたそうです。
※CSO・・・Civil Society Organizations(市民社会組織)の略。NPO法人や市民活動団体、自治会といった組織・団体を包括的に呼称している。
着任1年目は県内の団体関係者と会い、1,000枚以上の名刺を交換してきた野見山さん。2年目は足場とする団体を決め、関係性を築いてきました。3年目はどのように関わってきたのでしょうか。
野見山さん(以下、野見山) 3年目は、これまでに携わってきた3つの団体に週1回ペースで顔を出すようにしています。
1年目に事務局スタッフとしての役割を担わせていただいていた一般社団法人佐賀災害支援プラットフォーム(以下、SPF)とは、事務局が大変なときにヘルプで行ったり、呼ばれたときにセミナーの講師をやるぐらいの関係性に落ち着いてます。災害の活動って生半可にできなくて、やるならどっぷりやらないといけない。そういう点で、向き合い方が難しい部分もあります。
同じく1年目から関わっている「ごみダイエット」プロジェクトには、年間を通して何かしらの形で携わっています。冬の時期には「サガ・ライトファンタジー」、夏の時期には「佐賀城下栄の国まつり」というイベントがあります。イベントの3〜4ヶ月前ぐらいから会議を重ねて、役割分担をして準備をします。イベントのあと、商店街の人たちが夜中まで大変な思いをしてごみ拾いをやらなければいけないという課題を解決するために、「ごみダイエット」をしてくれる学生や社会人を集めています。他にも、イベントのステージ設営や音響をやったりと、手伝えることは何でもやっていますね。
 楽しそうに活動を振り返る野見山さん。笑顔からも充実した活動が伺えます。
楽しそうに活動を振り返る野見山さん。笑顔からも充実した活動が伺えます。
野見山 2年目から携わっているNPO法人まちの根太では、引き続き、明治40年に建てられた旧枝梅酒造という歴史ある建物をどう活かすかという検討を進めています。蔵の解体も進み、佐賀県初の「SAGA ART FAIR」を2025年3月に開催します。海外からもアーティストを呼んで、作品展示やライブペイント、音楽とコラボした創作活動などをやる予定です。東京や福岡の大都市圏では結構アートフェアをやってるんですけど、佐賀ではなかなかそういうのがない。一方で、佐賀大学には芸術の学部がある。そういう若手アーティストたちの活躍の場が足りないんですよ。
最近の僕の役割としては、「SAGA ART FAIR」のクラウドファンディングの立ち上げと支援です。この場所に若手経営者とかが集まってくれるように仕向けています。少しずつですが、この場所のことを「いいね」と言ってくれる人が増えてきました。他にも、会場としての環境を整えてもいます。壁の修繕とか実作業が多いです(笑)。解体した蔵の中にあった大きな樽をばらしてそれを壁にしたり。めっちゃかっこよく仕上がったんですよ。
関わってきた団体との繋がりをさらに深めてきた野見山さん。それぞれの場所で、なくてはならない存在のようです。
 関わる団体が増えるごとに名刺も増えていったそうです。いろんな顔を持ち合わせることで、人と人、団体と人をつなげてきました。
関わる団体が増えるごとに名刺も増えていったそうです。いろんな顔を持ち合わせることで、人と人、団体と人をつなげてきました。
2024年の元日に発生した能登半島地震。佐賀で発生した大雨の際も災害支援に携わった経験のある野見山さんは、被災地に駆けつけました。発災からの時間経過とともに支援の内容も変わっていったそうです。
野見山 休みをとって、4回石川県へボランティアに行きました。 1回目は発災2週間ほどで入り、現場にどんどん届く物資倉庫の管理をしました。企業から物資を集めて被災地に支援する公益社団法人Civic ForceとSPFが協力関係にあり、僕が大型免許を取っていたことをご存じでお声掛けをいただきました。ケースで届く大量の寄付の中身が何か、何個あるかなど、全部仕分けして管理表を作る。フォークリフトで積み上げて、ボンボン飛んでくる「○○ください」という問い合わせにすぐ返事をする。10日間くらいはそんな活動をしていました。
2回目は2月に認定NPO法人日本レスキュー協会の佐賀県支部であるMOREWAN(以下、モアワン)のサポートでボランティアに行きました。発災から1ヶ月以上経つと、ペットを飼っている人が避難所に来られないという問題が出てくるんです。犬や猫を飼ってるから避難所には行けませんという人が、物資を受け取れない。他にも、人間が優先で、ペットに関わる物資はすごく不足するという問題もあります。モアワンが集めてきたペット関連の物資を佐賀から発送してもらい、僕が石川県で受け取り、避難所ごとに配る仕事をしました。避難所に配るだけでなく、避難されている人に「近所でペットを飼っていて避難所に来ていない人はいませんか?」と聞き込みをして、物資を届けたり。
ただのペット支援だと思ったら大間違いで、結局ペットを飼っている人間の支援なんです。だけど「ペット支援で来ました」と言うと、「ペットより人の生活を確保する方が優先だ」と言われて後回しにされたり、現地でうまく支援に入れなかったりすることもありました。「佐賀での経験上、モアワンのようなペット支援があった方が避難所がうまく回りますよ」とお伝えをしてまわったり。仕事は尽きないですね。
 一口に災害支援と言ってもいろいろな支援の形があるようです。人に、現場に寄り添いながら支援を続けます。
一口に災害支援と言ってもいろいろな支援の形があるようです。人に、現場に寄り添いながら支援を続けます。
野見山 3回目は10月。重機を使って9月の大雨で被害にあったお家の泥出しと荷物出しをしに行きました。ちょっとずつ震災から立ち直ってきていたんですけど、場所によっては復興の「やり直し」でした。普通だったら支援を受ける住民さんたちの反応も「じゃあ片付け頑張りましょう。よろしくお願いします」で始まるんですけど、始まらないんですよ。「もう片付けんでよか」みたいな。気持ちが折れてしまっている。「そんなこと言わんで一旦片付けよう」ってやる気を引き出してやっと、「やれるだけやろうかね」と作業が始まる。気持ちの支援が大切な時期でした。
実際に荷物出しを手伝うと、もう使えないような物が多いんですけど、住民さんたちにとっては思い入れがあるからなかなか捨てられない。ただ、活動の時間にも限りがあります。そんな時は僕の被災地支援の経験をお伝えしたり、どうしても捨てきれないものは「じゃあこの箱いっぱいだけにしましょうね」とか、気持ちに寄り添いながらお手伝いしていきました。1日ご一緒すると、すごく昔からの友達だったみたいに関係性が深まるんですね。僕が佐賀に帰ってきてからも「次いつ来るの?」って電話があったりします。やっぱり寂しい気持ちもあるんだろうと思います。
 重機やフォークリフト、大型免許などたくさんの資格も取得し、あちこちで活躍の幅を広げています。
重機やフォークリフト、大型免許などたくさんの資格も取得し、あちこちで活躍の幅を広げています。
野見山 4回目は12月。企業版ふるさと納税のアテンドと支援のために行きました。企業版ふるさと納税の事例をたくさん持っている会社の方を、輪島市や珠洲市、七尾市の防災関係の担当者や僕が繋がっている石川県庁の方、NPOなどの災害支援側の人にもどんどんお繋ぎしました。この人だったらどんな支援を石川県に持ってこれるのか、どんなことができるんだろうかと、僕もワクワクしながら案内しました。
能登には今もボランティアが必要です。9月の大雨で水害が起きたところにはいくらか集まりましたが、それも減ってきています。比較的被害が少なかった地域や元々地震の影響が薄かったところほど、ボランティアがだいぶ減ってしまっていることが課題の1つですね。
佐賀での災害支援の経験を生かし、混乱が生じる被災地でより多くの方に支援の手が届くように動いた野見山さん。冷静な判断と経験が能登の支援に活かされました。
 水道が止まって最初に困るのは飲料水ではなくて実はトイレだそうです。野見山さん自身もこれを機に防災バッグを準備したそうです。
水道が止まって最初に困るのは飲料水ではなくて実はトイレだそうです。野見山さん自身もこれを機に防災バッグを準備したそうです。
卒業後も佐賀で暮らしていくために新たな事業モデルを確立したという野見山さん。どんなアイデアが閃いたのでしょうか。
野見山 卒業後に僕が食べていけないと、結局活動を持続できないので、3年目は僕の収入を得ることを第一優先で考えました。これまでやってきた活動を半分くらいに抑えて、ファンドレイジングというCSOの資金調達を本業にするための試行錯誤をしています。
具体的には、企業側にどんどん入ったり、経営者が集まる場所に顔を出したりして、寄付のアピールをしてまわっています。CSOに寄付をしてもらって、集まった寄付の一部を手数料としていただくスタイルの事業です。1年前くらいから少しずつ進めていたんですけど、最初は単純に寄付のお願いで回っていたからか、なかなかうまくいかなくて。どうしたらうまくいくかなってことで「経費削減型寄付」が出てきました。
経営者が集まる会の社長さんの中にも、社会貢献に前向きな方が意外に多いんですよ。会社のテーマとして地域貢献を掲げていることもあるので、「実は近くに社会のためになる良い活動をしている団体さんがあるんですよ」と紹介して寄付に繋げたり。でも、いきなり「寄付ください」ってなかなかハードルが高い。そこで、僕の知り合いの経費削減コンサルタントの方を連れていって、「経費を削減するので、下がった費用の半分を寄付してください」とお願いすることを思いつきました。「下がった分なら寄付するよ」となりやすいし、メリットもある。ドネーション文化の一歩目というか、初めての寄付のお手伝いをしています。
これまで築いてきた経営者の方たちとの繋がりの中で「野見山くんの言うことなら」「そんな無茶な話じゃなかったらやるよ」ぐらいの関係性ができた社長さんにお願いに行っています。すでに商談が終わってるところが佐賀だけで20件以上あって、経費削減の効果も出ています。「ファンドレイジング佐賀」という屋号で始めて、軌道に乗ったら法人格を取ろうと考えてます。

 いろんな工夫が詰まった事務所カー。ファンドレイジングにも災害支援にもこの車で駆けつけます。
いろんな工夫が詰まった事務所カー。ファンドレイジングにも災害支援にもこの車で駆けつけます。
野見山 今後は、他県からの寄付を佐賀に集めることも考えています。そうすると佐賀にいないことが結構多い。そのときに一番高いのが宿泊費です。それで起業支援補助金を使って事務所カーを作りました。デスクとパソコンがちゃんとあって、寝れる。濾過器も付けて、雨水とか川の水も飲めるようにして。ちゃんと仕事ができて、災害時の活動もできる車に改造しました。これから活用するのが楽しみです。
3年間を振り返ってみると本当に楽しかったですね。全然まだまだ協力隊を続けていたいぐらいです(笑)。今まで触れることのなかった人たちの活動にたくさん触れることのできた3年間だったので、その経験を事業として活かしていきたいです。3年目に入ってからは、こんなことしたいと思ったら、「それってあの人が得意だったな!」というのが頭の中でピピッときて、すぐ繋がれるということが増えました。この感じが心地良くて、3年間頑張ってきたんだなと思えます。最初から佐賀に住み続けるつもりだったので、佐賀に残れる目途が立ったことも嬉しいですね。
人や団体と積極的に繋がり、そして繋げることで多くの課題解決に結びつけてきた野見山さん。その結果、企業、NPO・CSOそれぞれにメリットのある事業モデルが誕生しました。「いきなり寄付はハードルが高いと思うんですが、興味のある活動でいいので参加してみてほしい」という野見山さん。小さな一歩から広がるものがありそうです。
※この記事は2024年12月取材時点のものです。
取材・文 眞子紀子

追記
野見山さんは2025年3月末に任期を満了され、SML(佐賀県地域おこし協力隊)を卒業されました。卒業後は、記事中にあるように佐賀に定住し、ファンドレイジングの仕事を続けていきます。たくさんの人と団体を繋いだご縁をもとに益々活動の幅が広がりそうです!
野見山さん、3年間お疲れ様でした。