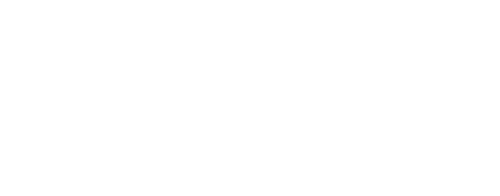
2024
PROJECT09 | 市民活動と人 隊員活動レポート

国籍や性別を問わず人と人のつながりから社会課題の解決を目指す、CSO連携型地域おこし協力隊「さがむすび隊」として活動してきた古泉志保さん(以下、古泉さん)。認定NPO法人地球市民の会に所属し、ウクライナ避難民の受け入れや、受け入れ後の支援などで尽力してこられました。多文化共生とジェンダーをテーマに活動を進める古泉さんは、地域おこし協力隊として最後の3年目をどのように過ごされたのでしょうか。
※CSO・・・Civil Society Organizations(市民社会組織)の略。NPO法人や市民活動団体、自治会といった組織・団体を包括的に呼称している。
着任してすぐ、官民連携でウクライナ避難民を受け入れる「SAGA Ukeire Network~ウクライナひまわりプロジェクト~」の事務局として39人ものウクライナ避難民の受け入れ対応をすることとなった古泉さん。他にも、相手の目線に立って、日本人と外国人の垣根を下げるような企画を立案してきました。今年もいろいろな場で活躍してこられたようです。
古泉さん(以下、古泉) 現在、ウクライナ避難民の新しい受け入れはストップしています。そこで今は、来日されている方ができるだけ佐賀県に馴染めるように、県民向けの「ウクライナ理解講座」を開催しています。私も、ウクライナの祈りを込めたモタンカ人形をつくるワークショップを担当しました。昨年、地球市民の会にウクライナ関係の仕事をしてくれるスタッフが新たに2名加わったので、仕事のボリュームとしても以前ほど大変ではなくなりましたね。
 モタンカ人形はウクライナで古くから作られている伝統的なお守り人形。毛糸や布のはぎれをぐるぐる巻いてつくるそうです。
モタンカ人形はウクライナで古くから作られている伝統的なお守り人形。毛糸や布のはぎれをぐるぐる巻いてつくるそうです。
古泉 異文化に対する理解がない状態でいきなり違う文化を持った人が来ても、お互いにうまくいかないから、「受け入れるときはこんなことに注意しましょう」みたいな認識を広げていけたらと思っています。その一つとして、お茶を飲みながら異文化交流をする「世界のお茶会」を開催してきました。初年度は7回、去年は4回。3年目で認知度は若干上がってきたかな。県内の地域おこし協力隊ともコラボしています。研修会などで集まった時に異文化交流の活動をPRして、興味を持ってくれた隊員とお茶会を共催するのです。お互いにルーツが違う人同士が交流しながら、「こういう方がいらっしゃって、こんな仕事をしていて、故郷の文化はこんな感じで」ということを伝え合う場所になっています。
講演活動も行っています。県内の学校などから地球市民の会にSDGsについて話してくださいという依頼が来るので、今年は全部、私が担当しています。それとは別に、私の好きなテーマで講演するお仕事が月に2件あります。そのうちの一つは、地球市民の会関連団体の学童のプログラムの一貫で、子どもたち向けに「真の国際人の養成」をテーマにしています。今、話題にしているのは「社会の変え方」。スウェーデンの社会の教科書には「社会の変え方」が載っているらしいんですよ。じゃあ日本の教科書って何が書いてあるのかな。小学生にも困っていることはいっぱいあるはずだから。みんな、自分が生きやすいように社会を変えてもいいんですよっていうのをお伝えしたくて。こういうことが世界を良くすることにも繋がるんじゃないかなと考えています。
まだ頭の柔軟な子どもたちに、社会って変えられないもの、我慢するしかないものじゃなくて、自分たちが生きやすいように変えていくものなんだっていうことを伝えるために、毎月考えに考えて、講演内容を構成しています。こういう場を定期的に持たせていただくと、自分の成長にも繋がるからすごくありがたいですね。
2年にわたる活動がさらに花開いた3年目。持ち前のフットワークと企画力、そして人を巻き込む力、古泉さんの魅力でいろいろなイベントを成功させてきました。さらに、「気づき」を与える種まきが進んでいます。

 多忙な日々を乗り越えて笑顔で活動する古泉さん。3年間でたくさんのことを身につけたのではないでしょうか。
多忙な日々を乗り越えて笑顔で活動する古泉さん。3年間でたくさんのことを身につけたのではないでしょうか。
友人であるエチオピア出身のデレセさん一家と関わるようになって、テーマとしてきた「多文化共生とジェンダー」に対する問題意識をさらに強くしたそうです。
古泉 私が以前エチオピアに住んでいたこともあって、佐賀に来てすぐにエチオピア人のデレセさんを紹介してもらいました。お友達になってもう3年目。「世界のお茶会」も協力してもらっています。あるときデレセさんから、「去年、エチオピアに学校を作ったんだよね。でも全然校舎が足りなくて」という話を聞きました。幼稚園児を中心に300人が入れる学校を作ったそうなんです。その子たちは順次卒業して小学生になっていくんですけど、また新たな幼稚園児も300人入ってくる。すでにぎゅうぎゅう詰めなのに、教室が足りなくなってしまう、と困っていました。
そこで、地球市民の会でクラウドファンディングのサポート業務を担当していることもあり、クラウドファンディングに挑戦してみることになったんですね。設定した目標額の300万円に対して約174万円が集まり、校舎を建てるのに役立ててもらいました。デレセさんは本当に真面目な方です。日本の大学に通った経験があり、日本みたいな学校教育を故郷の子たちに受けさせたいという思いをお持ちでした。
 はじめてのクラウドファンディングの支援。目標額には届かなかったものの大きな力になったはず。
はじめてのクラウドファンディングの支援。目標額には届かなかったものの大きな力になったはず。
古泉 デレセさんご一家に限らないんですが、夫・父は日本語が話せて仕事もある、子どもたちは日本の学校で日本語を学び、友だちもどんどんできていく。一方で、妻・母は、家事・育児・仕事で忙しくて日本語を学ぶ機会が十分に確保できず、なかなかコミュニティに加われないという状況があります。私もかつて同じような状況を経験しましたが、日本中で、もっと言えば世界中でこうした状況が起きていると思います。こういったことに気づくこと、改善しようとしていくことが、「多文化共生」を進めるうえで絶対に必要だと強く思っています。
社会と関わる機会や深さによって生まれる「多文化共生」と「ジェンダー」の課題。古泉さんの問題意識と課題に対する意欲はますます高まります。
3年目を迎えた古泉さんは当初からやりたかったジェンダーに関する団体を立ち上げました。そこには若い世代の参加もあり、安心して語り合える場となっています。
古泉 今年の5月に「ミモザイコール(Mimosequal)」という新しい団体を作ったんですよ。私が代表で大人の女性がもう1人、女子高校生が2人っていう素敵なメンバーで、今年はワークショップを4回企画しました。ずっとジェンダーをテーマに何かやりたいなと思っていたのですが、地球市民の会に「ボランティアしたいんです」って電話をかけてきてくれた女子高校生がいて、その子がすごくジェンダーに興味があるということで一緒に団体を立ち上げました。団体名はその子が考えてくれて、国際女性デーのシンボルフラワーである「ミモザ」と平等を意味する「イコール」を組み合わせたものです。

古泉 ジェンダーの“もやもや”を一緒に何とかしようというワークショップで、1回目は「性別に基づくもやもや共有会」と題して日常で感じるもやもやをみんなで喋って聞き合うという会。2回目は「日常生活で感じるもやもやについてのプチ講義」。例えば職場とかで、「何か嫌なんだけど」って思ったことに「セクシュアルハラスメント」って具体的な名前がつくことで問題になって話題にしやすくなる。もやもやを口に出すことに意味があるっていう内容です。
メンバーの女子高校生が感じていたもやもやは家庭ですね。「お母さんだけが家事してるぞ」、「お父さんはグダグダして茶碗も持って行かない」みたいな。私にも兄がいますが、子どものころは私ばかり家の手伝いをさせられました。ただ、その子の周りにはジェンダーに興味ある人がいっぱいいるらしいんですよ。それがデフォルトで、「ジェンダー平等じゃない社会なんてありえないでしょ」ぐらいの感じらしいです。
ワークショップには中学生や社会人も来てくれましたし、ちょっとずつ良くはなってきていると思います。とはいえ全然変わっていないものもありますよね。世の中は男女平等って建前のもとに進んでるのに「実際にはそうじゃないじゃん」って感じる若者がたくさんいると思うんです。

 当たり前のことを当たり前にすることは案外難しいものです。古泉さんの熱い情熱が未来を切り拓いてくれそうです。
当たり前のことを当たり前にすることは案外難しいものです。古泉さんの熱い情熱が未来を切り拓いてくれそうです。
古泉 上の世代から「我慢するのが大人だ」とか、「当たり前」って言われてきて、結果、いまでも同じことが起きているんです。そういうのを再生産したくない。それに加担したくない、っていう人はいっぱいいると思うんですけど、こういうことは誰にでも話せる話題ではないので、こういうワークショップで同志を見つけて、一緒にやっていきたいなと思っています。あなたが我慢しちゃうことによって、あなたの娘も同じ目に遭うかもしれないんだってことに気づいてほしいんです。
地域おこし協力隊3年目はこれまでの活動と合わせてクラウドファンディングをやってみたり、ミモザイコールを立ち上げたりと、これからを見据えた活動で忙しいですね。卒業後は「起業支援補助金」も活用しながら、佐賀で「多文化共生とジェンダー」を軸に活動していく予定なので、起業に向けた準備もしています。
古泉さんの伝えたい「気づき」は、どうかすると気づかないまま飲み込んだり、雰囲気や社会の流れに合わせたりしてしまうような小さな“もやもや”たち。ですが、その気づきに向き合うことで、社会が変わる一石になるかもしれません。ちょっとすっきりしに、古泉さんに会いに出かけてみてはいかがでしょうか。
※この記事は2024年11月取材時点のものです。
取材・文 眞子紀子
追記
古泉さんは2025年3月末に任期を満了され、SML(佐賀県地域おこし協力隊)を卒業されました。卒業後は記事中にあるように佐賀に残り「多文化共生とジェンダー」を軸に起業し、講演やワークショップ、コンサルティングをしていく予定です。世界を、社会を少しずつ良くしていくことに奔走する古泉さんのこれからの活躍から目が離せません!
古泉さん、3年間お疲れ様でした。