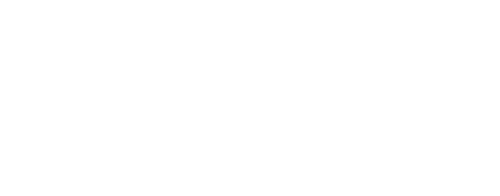
2024
PROJECT06 | 外国人と友だち 隊員活動レポート

佐賀で暮らす日本人と外国人をつなぎ、円滑なコミュニケーションを築く機会を創出する「多文化コミュニケーションプランナー」の武田有里子さん(以下、武田さん)。祖父母との思い出が詰まった佐賀県に移住し、日本人と外国人の両方に関わり続け、目では見えないさまざまな壁を崩すために奮闘してきました。
県内全体を巡りながら、活動してきた武田さん。地域の人と、そこに暮らす外国人とをつないできました。両者が接する機会をつくり続けたことで、どんな変化が生まれてきたのでしょうか。
武田さん(以下、武田) 3昨年から佐賀県立白石高等学校で、「総合的な探究の時間」という授業にアドバイザーのような立ち位置で入らせていただいています。「総合的な探究の時間」は、生徒の興味・関心のあるテーマでグループを作り、学んだことを地域に還元する授業です。私は「多文化共生」のテーマを担当しました。
昨年の高校1年生の授業では、「やさしい日本語」を学んだり、地域の外国人と日本人の交流を一緒に考え実践しました。外国人の皆さんと料理交流とジェンガをしたのですが、ただジェンガをするだけでなく、ジェンガにランダムで質問シールを貼り、抜いたジェンガの質問に答えながら交流していくという仕掛けを高校生が自ら考えました。ジェンガに書かれた質問が授業で教えた「やさしい日本語」で書いてあったことに「ちゃんと伝わっていたんだな」と思いました。
 おじいちゃん、おばあちゃんからこどもまでいろんな世代と共に歩んできた武田さん。その経験が実りつつあるようです。
おじいちゃん、おばあちゃんからこどもまでいろんな世代と共に歩んできた武田さん。その経験が実りつつあるようです。
武田 1年で終わる授業だと思っていたのですが、思いがけずメンバー全員が「多文化共生」のテーマを2年生でも引き続き深めたいと選んでくれ、継続することになりました。2年目では料理交流でも関わってもらった外国人のマーラーさんが働く介護施設に行き、マーラーさんと一緒に働く外国人の皆さんと、じっくり話す場を持ちました。
1年生のときには、外国人に対して「何を話していいかわからないし、言葉も通じるかわからないから怖い」と言っていたのに、2年生になると「意外と言葉が通じるんだなって思った。もっと話したい!」と、高校生に気持ちの変化があったことが印象的です。「多文化共生」に興味があるグループにしては、少しおとなしさを感じる状況もあったのですが、高校生なりに色々なことを感じ取っているのだなと思いました。
このような変化が見られたのは嬉しいですね。この分野は交流の機会があったとしても、数十年後になってようやくやってきたことが実を結ぶ、ということも多いと聞いています。「早く何か実績を残さないと」と、焦る私でしたが、先輩である多文化社会コーディネーターの北御門さんから、「焦らずに着実にやっていこう」とアドバイスをもらったことでやってこれました。
高校生と共に、考え歩んできた武田さん。人の心の機微がわかるからこそ、そっと背中を押すことができたのではないでしょうか。わずかな変化の積み重ねが「多文化共生」の新たな芽を生んだようです。
 3年間の活動を支えてくれた北御門さんと一緒に。頼れる先輩と並ぶ姿にも力強さを感じます。
3年間の活動を支えてくれた北御門さんと一緒に。頼れる先輩と並ぶ姿にも力強さを感じます。
県内のいろいろな交流の場に足を運んできた武田さんだからこそ見えた視点から、新たな交流の場を設け、動画作成もスタートさせました。
武田 外国人に対する印象を少しずつ変えるような活動をしてきたつもりですが、1人で広めても大きく変わることはなくて。私が発信力の強い人につながって、その人が「多文化共生」を広めてくれて、そこからつながったまた違う人がさらに広める、といったアクションを起こせば、もっと広がっていくな、とずっと考えてきました。
2024年11月からは「世界にふれる夜のお茶会」を始めてみました。県庁職員を始めとした日本人が外国人と一緒にお茶を飲みながらお話しするという気軽な会を月に1度、県庁の地下にあるカフェエリアSAGA CHIKA で開催しました。
毎回、日本人と外国人が半々ぐらいで約20人が集まりました。参加している外国人には、仕事の情報がほしい人も、楽しく話したいという人もいます。日本人からも外国人が佐賀に来た理由や佐賀の魅力等をたくさん質問していました。軽いテーマから深刻なテーマまで話題はつきません。参加した外国人からは「学校や職場を越えた人と出会って、いろんな話をするのが楽しい」とか、こどものいるお母さんは「子育ての悩みを相談できて良かった」といった感想をいただきました。
 外国人からも日本人からも笑顔とやる気を引き出す武田さん。できること、自信を持てることが3年間で増えたのではないでしょうか。
外国人からも日本人からも笑顔とやる気を引き出す武田さん。できること、自信を持てることが3年間で増えたのではないでしょうか。
武田 もともと国際交流に興味がない、という方々にも広がってほしいなと思っています。興味がない人って、友達の誘いや引っ張り込んでくれる人がいないと交流イベントにはなかなか来てくれません。市町で開催したワークショップもそうだったんですが、「孫が行きたいって言ったから、一緒に付いてきました」というおばあちゃんがいたり、「こどもに外国人と接する経験をさせたくて連れてきました」というお母さんお父さんがいたり。小さなところから徐々に広げていけたら、その楽しさやワクワクは広がると思います。
他にも地域日本語教室の紹介動画の作成を始めました。日本語教室というと、「日本語を外国人に教える場所」というイメージがあると思いますが、ただ外国人と話したい日本人でも、日本人と話したい外国人でも、どちらも気軽に来て良い場所なんです。教室によって活動の色は様々ですが、どの教室も地域の外国人の居場所としての役割を担っています。みんなが集まる温かい場所です。運営している方々が工夫しながら情報発信されていますが、写真などでは伝わりにくい部分があるので、動画にしたら雰囲気も届くんじゃないかと思い、紹介動画の作成をはじめました。
それに関連して、3名の外国人を「たぶんかYouTuber」に任命しました。私だけではなくて、外国人視点の動画もあると良いのではないかと思い、7か月間一緒に活動をしました。3月には、動画の成果発表会を開催して、20名の方々に観てもらいました。
外国語を話せないと、外国人との交流はハードルが高いと感じる人も少なくありません。武田さんはそんなためらいのような気持ちを汲み取り、交流しやすい雰囲気をつくり出してきました。3年目だからこそできた場づくりと情報発信のおかげで、交流への一歩が踏み出せる人もたくさんいるのではないでしょうか。
 気軽に多文化交流の様子が見られるYouTube動画を配信中。今後の更新も楽しみです。
気軽に多文化交流の様子が見られるYouTube動画を配信中。今後の更新も楽しみです。
武田さんに改めて「多文化コミュニケーションプランナー」とはどんな存在か。そして必要な視点とは何かを聞いてみました。
武田 「多文化コミュニケーションプランナー」は外国人だけではなく、地域の日本人ともコミュニケーションをとって、人とのつながりのインフラを整えるような仕事だと思っています。佐賀で暮らす外国人と日本人のどちらとも関りをもち、両者をつなげるということを目標にしてきました。普段の生活でお互いのことを身近に感じる機会が少ない両者をどうつなげていくのか。そして、そのつながりをどう継続させるのかが大切です。
たとえば、外国人に「何かをしてあげたい」という気持ちは大切だと思いますが、それだと「支援」になってしまう。「支援」じゃなくて、外国人も地域の中で活躍できる場を作り、力を発揮できるようにサポートすることが大切なのではないかと思っています。
「野菜作り交流」で関わっている集落では、芋ほりや餅つきなどの楽しいイベントには外国人にも参加を呼びかけるようですが、清掃活動には声かけをしないと区長さんから聞きました。そこには「声をかけても清掃活動にはどうせ来ないだろう」という気持ちがありました。「外国人も地域住民の一員なので呼んでみては?」と話して、区長さんが声をかけてみると、実際に何人か清掃活動に来てくれたそうです。「すごい掃除頑張ってくれたんだよ。来てくれると思わなかったからびっくりしたよー」と嬉しそうに話されていたのが印象的です。
ただ楽しい時間を共有するだけではなく地域で支え合う関係性が築けたらと思います。たとえば何かの災害が起きたときに、外国人が「いつもお世話になってる○○さん(日本人)大丈夫かな?」と気にかけたり、逆に日本人も「あそこの○○さん(外国人)無事かな?」と安全を確認し合う関係性が理想ですよね。それで助かる命も増えるんじゃないかなって思います。
 悩んだことも多かったと話す武田さんですが、3年間で耕した土壌にはたくさんの芽が出ていそうです。
悩んだことも多かったと話す武田さんですが、3年間で耕した土壌にはたくさんの芽が出ていそうです。
武田 最初は地域の方々から「どうせ仲良くなっても数年で外国人は帰ってしまっていなくなる。交流しても意味がないのでは?」と言われていました。でも、帰国する外国人がいても、地域として外国人を受け入れる環境があれば、新しく佐賀に来た外国人も暮らしやすいと思います。そういったサイクルの中で、外国人と日本人が一緒に地域をつくっていくという雰囲気が生まれていくのだと思います。
技能実習生たちの勤め先でお世話係をされていた方がちょうど定年退職になったのですが、後任の方を紹介してくださいました。有難いことに後任の方からも「引き継いで同じようにやっていきたい」と言っていただきました。地域の人も、企業の人も、技能実習生たちも、入れ替わりがあるのは当然です。次の人に引き継いでいくという関係性ができていることが大切なのだと思います。
今の日本社会は、外国人の力がないと成り立たない場面がたくさん生まれており、地域で生活する外国人も増加しています。「そのうち日本人がいなくなってしまうのでは」と、不安を感じる日本人の声もあり、実際に、外国人のほうが多い地域も出てきました。今あらためて大切なのは、外国人と共に暮らす地域のことをどう受け止めるか、ということだと思います。「せっかく一緒に暮らしているのだから、地域の行事や活動にも気軽に参加してもらいたい」と思えるのか、それとも、「どうせ外国人はすぐ帰るし、関わっても意味なんかない」と距離を置いてしまうのか。この小さな受け止め方の違いが地域のこれからを大きく変えていくように感じています。
「多文化共生が地域活性化とどう関係があるの?」と感じる方もいるかもしれません。特産品開発とかビジネスのように、すぐに成果が見えるものではないからです。でも、異なる文化や価値観を持つ人たちが地域で出会い、関わり合いながら暮らすことは、人と人との新しいつながりと地域の文化を生み出しています。「多文化共生」は目には見えにくくても、あたたかい地域のつながりを生み出すものであり、そのつながりこそが、これからの地域を支える大切な”インフラ”になると、活動を通して感じることができました。
武田さんが一生懸命耕してきた心のインフラが少しずつ整備され、「外国人」「日本人」ではなく、一つの地域としてのつながりが育ってきたようです。共に佐賀で暮らすからこそ、みんなが安心して生活できる環境を共につくっていくことが必要だと、武田さんは教えてくれました。
※この記事は2025年1月取材時点のものです。
取材・文 眞子紀子

追記
武田さんは2025年3月末に任期を満了され、SML(佐賀県地域おこし協力隊)を卒業されました。卒業後は、佐賀県さが多文化共生推進課に残り、引き続き「多文化共生」の輪を広げていく仕事をされるそうです。これからも「外国人」「日本人」ではなく、共に佐賀で暮らす人として地域のつながりが深まることが楽しみですね。
武田さん、3年間お疲れ様でした。