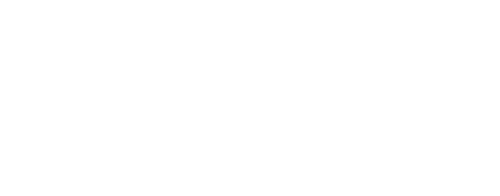
2022
PROJECT02 | 里と人 隊員活動レポート

山菜は里山のめぐみの1つです。山菜をおいしく学んでおいしく伝える「料理人見習い」の仕事は、先人たちから里山の暮らしの知恵を学び、その情報を伝えることで佐賀の里山のファンを増やすことを目指しています。
2023年2月にこのプロジェクトに着任したのは、食べることが大好きだという日高涼子さん(以下、日高さん)。1年目はどんな日々を過ごしてきたのでしょうか?
某有名コーヒーショップで長年接客や店舗運営をしてきた日高さん。東京での暮らしとは打って変わって、佐賀の里山に通う日々を過ごしています。どんな日々を過ごしているのでしょう。
日高さん(以下、日高) 今は1週間に1回くらい「森の香 菖蒲ご膳」さんに通っています(以下、菖蒲ご膳)。季節ごとに、どんな山野草や野菜、花が使われているかを少しずつ把握していっています。お店のお手伝いもしていて、皿洗いの合間に、料理を習う、知るということが多いです。
基本は、和え物、酢の物、煮物、天ぷらなどで、季節によって中身の素材が変わります。お花だと、最近はクズ、ヤブカンゾウ、ギボウシ……。ヤブカンゾウは葉っぱの状態だと判別できなくて、花が咲いてはじめて「あ! ここに咲いてたんだ! この葉っぱだったんだ!」と気づきます。

 厨房で一緒に料理をしたり、お弁当におかずを詰めるお手伝いをしたり。ちょっとしたことの1つ1つの積み重ねができることの幅を広げてくれそうです。
厨房で一緒に料理をしたり、お弁当におかずを詰めるお手伝いをしたり。ちょっとしたことの1つ1つの積み重ねができることの幅を広げてくれそうです。
日高 実家に帰ったときに、ギボウシやユキノシタが生えているのを見つけて「あるじゃん!」ってなり、実は山野草がすごく身近だったことに気づきました。知らなかったことが少しずつわかるようになり、食材としての植物を知ることができるのは本当に楽しいです。
今までよりも咲いている花や、植物に目が行くようになったし、そんな生活ができることがうれしいです。
新しい暮らしと仕事の中に楽しみや新鮮さを見つけている日高さん。充実した日々かと思いきや、まだまだ満足はいっていないようです。もう少し詳しく聞いてみましょう。
 まわりをきょろきょろ見渡しては、「これがここにあったんです! もう少しで収穫ですよ!」と色んなことを教えてくれる日高さん。
まわりをきょろきょろ見渡しては、「これがここにあったんです! もう少しで収穫ですよ!」と色んなことを教えてくれる日高さん。
日高 私自身は新しいことをたくさん学ぶことができたり、いろんな方からいろんな話を聞いたり、いろんなところへ行けて、すごく楽しいです。でも、まだまだ誰かの役に立てたり、何か課題を解決したり、ということにはつながっていないように感じています。
もしかしたら、もっと深く関われたら誰かの課題や悩みを引き出して一緒に何かできたりするのかもしれないですが、まだそこまでは至らなくて。私ばかりが楽しくてすみません! という気持ちです。
 自分が楽しいだけじゃなく誰かに還元したい、という日高さんのまっすぐな気持ちがあるからこそ、ついついみんな応援したくなるのかもしれません。
自分が楽しいだけじゃなく誰かに還元したい、という日高さんのまっすぐな気持ちがあるからこそ、ついついみんな応援したくなるのかもしれません。
日高 佐賀の山野草の先駆者でもある西要子さんもおっしゃっているのですが、実は九州は東北や北陸、北海道に比べると山野草の文化ってそんなに多くないのだと活動していく中で感じました。70、80代のおばあちゃんたちは、郷土料理には詳しいのですが、そもそもあまり山野草を食べる文化が浸透していないようです。
ワラビやフキなどオーソドックスなものは食べることが多いですが、ユキノシタやギボウシなどあまり浸透していない食べられる山野草については、おばあちゃん世代の中には「そんなもの食べてどうするの?」という方もいらっしゃいます(笑)。意外に、30~50代の方のほうが「これ食べれるんだよ!」とか、「知りたい」っていう方が多い印象です。

 この日の天ぷらはミゾソバ(桃色の花)とツユクサ(青い花)。どちらも日常的に食べる文化はないけれど、おいしく食べられる山の宝物です。逆に、みんなが食べるクリ、ムカゴ、ヨモギには暮らしの知恵が秘められています。
この日の天ぷらはミゾソバ(桃色の花)とツユクサ(青い花)。どちらも日常的に食べる文化はないけれど、おいしく食べられる山の宝物です。逆に、みんなが食べるクリ、ムカゴ、ヨモギには暮らしの知恵が秘められています。
日高 ある時、菖蒲ご膳で皆さんと、お盆の過ごし方の話が出たんです。皆さん同じ宗派なんですけど、各家庭ごとにちょっとずつやり方が違ったり。「この日にはこれを出さないといけないよね?」と、何をするのかがしっかり受け継がれていることもあれば「そうだったっけ?」と、少しずつ忘れられていることもあって。もうひと世代前の人は完璧に言えたけど、だんだんだんだん、はっきりと言えなくなっていることも出てきている。こうやって少しずついろんな文化が受け継がれなくなっていくんだと実感しました。
当初の山菜料理人見習いの仕事のことを考えると、受け継がれなくなっているものを受け継いで残していく、伝えていくということが核になっています。なので、何をどうやって伝えていこう。という迷いがあります。みんなが知っている文化として存在している山菜料理だと意外に数が少ない。郷土料理まで幅を広げると山菜料理からは離れてしまう。佐賀では文化としては存在していないけれど、身近にあって食べられる山野草も宝物だし……。何をどう伝えていくのかまだまだ悩んでいます。
暮らしの知恵としてそっと受け継がれてきた山の宝物、山野草に興味を持つ人が生まれたからこそ新たに育まれた山の宝物。そんな消えそうで消えない山の恵みを、日高さんは悩みながら少しずつ集めています。
 ツユクサをただの雑草と思うのか、宝物と思うのかは人それぞれ。正解はないけれど、暮らしの中にたくさんの宝物があったとしたら、今より少し豊かな暮らしになりそうです。
ツユクサをただの雑草と思うのか、宝物と思うのかは人それぞれ。正解はないけれど、暮らしの中にたくさんの宝物があったとしたら、今より少し豊かな暮らしになりそうです。
悩みつつも少しずつ歩みを進める日高さん。菖蒲ご膳以外にも県内のあちこちを訪ね歩きながら、新しいことに挑戦しているようです。
日高 菖蒲ご膳さんの他にも、太良・鹿島エリアや、みやき町にも通っています。山の会議(仮)という、私が所属する佐賀県庁のさが創生推進が主催している「山についてみんなで考える会」があるのですが、その会議の際にも山菜天ぷらを振る舞いました。本当は懇親会で皆さんに振る舞う予定だったのですが、新型コロナウイルスの関係で懇親会が中止になり、一部の関係者にだけでしたが、山菜天ぷらを食べてもらいました。
太良町の元役場職員の新宮さんと多良岳のガイドをされている池田さんと一緒に、山菜を採りに行ったり、新宮さんのお家にもお邪魔したりして、おじいちゃんおばあちゃんの家ができたような感じでうれしかったです。
 SNS用の写真を撮る日高さん。写真やライティングの技術も高めたいそうです。
SNS用の写真を撮る日高さん。写真やライティングの技術も高めたいそうです。
日高 他にも、バナナとお茶で世界を平和にしようという!という面白いことを考えている佐賀市のbanachaの馬場さんという女性と一緒に、「野草茶を一緒に作ろう!」と盛り上がったり、馬場さんのお茶会で山野草のお菓子を出させてもらったりしました。
お茶会でお菓子を出すときには、菖蒲ご膳の佐保さんや森木さんにも協力していただき、初めて自分だけの作品を出すことができました。こういったチャレンジやイベントの企画などもこれからは少しずつ増やしたいと思っています。
たくさんインプットをしてきたので、これからはもっと頻繁にアウトプットとしてSNSでの情報発信や、イベント、教室といったものも、どんな形かはまだ決め切れていませんが増やしたいです。
たくさんの人に出会い、学びを深めた日々。2年目はどんなアウトプットが生まれるのでしょうか? 今から楽しみです。
取材・文 門脇恵
※この記事は2022年9月取材時点のものです。
 菖蒲ご膳の佐保さんと。山野草のことを学びつなぐ中で、人とのきずなや人生の宝物もつないでいるのかも。
菖蒲ご膳の佐保さんと。山野草のことを学びつなぐ中で、人とのきずなや人生の宝物もつないでいるのかも。