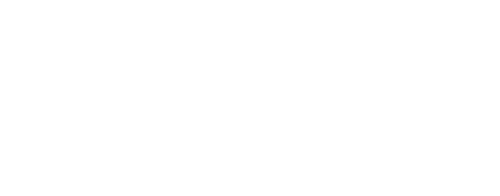
2024
PROJECT02 | 里と人 隊員活動レポート

春夏秋冬、その季節ならではの山野草を調理して食卓に並べる術を学んできた「山菜料理人見習い」の日髙涼子(ひだかりょうこ)さん。いろいろな先人たちと出会い、暮らしの中に取り入れる知識を積み重ねてきました。山野草の楽しみ方を広める機会も積極的につくってきた日髙さん。3年目はどんなわくわくを提供してくれたのでしょうか。
野草をお茶にして楽しむ自主イベントを開催するほど、知識と経験を蓄えた日髙さん。いろいろな地域に足を運び、多くの人と出会ったことで、山の課題も知りました。そこで、山の課題を解決につなげるイベントを企画したようです。
日髙さん(以下、日髙) “猫の手も借りたい”という誰かのお手伝いをする、「ねこのて会」を行っています。着任1年目に、柚子胡椒をつくる人手が足りないという話を聞き、「柚子胡椒のための柚子の皮すり」としてイベントを企画したところ、参加者同士でお喋りしながらの作業は楽しく、何ケースもあった柚子がどんどんなくなり、地域の方にも喜んでもらえたので、手ごたえを感じました。
実はこれまで、柚子胡椒を作るので手一杯で、柚子の中身は捨てていたそうです。そこで、参加者が柚子の中身を持ち帰ってポン酢にしたり酵素ジュースにしたり化粧水にしたりと、各々自由に活用できるよう促しました。フードロス削減につなげることができましたし、作業中に柚子の活用方法を話し合う時間も楽しかったです。

 柚子の良い香りと、皆さんのたのしそうな笑い声。お手伝いをきっかけにたくさんの輪が広がります。
柚子の良い香りと、皆さんのたのしそうな笑い声。お手伝いをきっかけにたくさんの輪が広がります。
日髙 フードロスは前の会社でも取り組んでいたキーワード。意識し始めてみると、意外と街だけでなく里山にもフードロスがあることが分かって。イベントにすることで人手を集め、フードロスを解消でき、地域の人の役にも立つ、「ねこのて会」はそんなイベントにできたと思います。
農家の人手不足とフードロスという課題を、楽しい体験として企画に変えた「ねこのて会」。初年度から参加している方もおり、毎年楽しみにされているそうです。日髙さんの気づきから、みんなが笑顔になれる場が生まれました。
日々の活動や出会った野草をインスタグラムに投稿し続けてきた日髙さん。たくさんの写真を通して、季節の移ろいが感じられます。発信のこだわりと、新たな企画「YASO LAB.(やそうラボ)」について聞いてみました。
日髙 「ねこのて会」をもっと展開させていきたかったんですが、「忙しいときに手伝ってくれるのは嬉しいけど、イベント化するまでは大変」という地域の方の声があり、実施に至ったのは「柚子の皮すり」と「発酵バンチャづくり」の2企画にとどまりました。 そこで新たに企画したのが「YASO LAB.」です。私自身がまだまだ教えられるレベルではないけれど、「一緒に実験してみませんか?」というスタンスのイベントです。採取から調理・加工、食事までの一連の流れを体験することで、イベント後に自分でも色々と試してもらえたらという思いがありました。山菜・野草に限らず、山らしい季節の手仕事も取り入れたいと考え、これまでに「味噌仕込み」、「よもぎもちづくり」、「どんぐりを味わう」の3回開催しました。
中でも特に、「どんぐりを味わう」の回の反響が大きかったです。1年程前に、どんぐりときのこが大好きでとても詳しい方と一緒に、スダジイというどんぐりを拾いに行ったのですが、落ちたあとに太陽の光でローストされていて、そのまま食べてもすごく美味しくて、とても感動したんです。それをみんなにも味わってほしいと思ってスダジイを持ち歩いてたんですけど、あんまり反応が良くなくて(笑)。やっぱり採取する過程があったり、どんぐりへの熱い思いを聞いてこそ感動できると思い、その方に協力をお願いし、イベントを開催しました。イベント用に作ったオープンチャットでは「どんぐりの魅力にハマりました」とか「好きな食べ物の一つにどんぐりと書けそうです」とか、反応してくれる方がすごく多かったです。

 改良を重ねたどんぐりクッキー。素朴でやさしくじんわりとおいしさが広がります。マテバシイという種類のどんぐりでつくるのがおすすめだそうです。
改良を重ねたどんぐりクッキー。素朴でやさしくじんわりとおいしさが広がります。マテバシイという種類のどんぐりでつくるのがおすすめだそうです。
日髙 イベントのやりとりをオープンチャットにしたことで、「味噌仕込み」のときは「カビ生えてきちゃった」との書き込みに「冷蔵庫に移してみたよ」とか、「そろそろ食べ始めたよ」みたいな、参加者同士だからわかるやりとりが生まれました。
私の企画するすべてのイベントに共通することですが、参加者の中に知識をお持ちの方が一定数いて、そうした方に教えてもらうことも多いです。また、イベント開催の他に、情報発信のためのインスタグラムを月に4回は更新するようにしています。最初の頃は知識を持っているわけでもない私が発信することにやりづらさも感じていたんですけど、「見習いなんだから見習いらしい風景を出そう!」と思うようになって、ハードルが下がりました。「こんなところに行ってこんなことを教えてもらいました」「この人がこう言ってました」みたいに、なるべく気負わず投稿しています。
心がけていたのは、内容をしっかり練ってからというよりは、時期を逃さないようにということ。例えば栗があるうちに、金木犀が咲いてるうちに投稿しなきゃ!って。投稿の中では、特にどんぐりクッキーの反響がすごく大きかったです。閲覧者の半分ぐらいは知らない人で、そこから他の投稿も見てくれていました。
日髙さんの投稿を見ていると、「これって食べられるんだ!」という情報がたくさんでてきます。自然豊かな佐賀に住んでいても、驚きの連続。
 暮らしの中に四季のうつろいと先人たちの知恵を取り入れてきた日髙さん。山菜アドバイザーの資格も取得しました。
暮らしの中に四季のうつろいと先人たちの知恵を取り入れてきた日髙さん。山菜アドバイザーの資格も取得しました。
これまでの知識や体験、そして人との出会いをまとめたいと、冊子のようなカレンダーの制作を進めているという日髙さん。どんなものが出来上がるのでしょうか。
日髙 実は佐賀県外でやりたいことが見つかり佐賀を離れることにしたため、3年間の学びや人との出会いをしっかりと残したいと思い、冊子にまとめることにしました。
山菜や野草に関する知識や活用方法はまだまだプロには及ばないので、題を「野に親しむ見習い暦」とし、県内で身近に楽しめる山菜や野草から季節を感じられるように意識して制作しました。カレンダーのような構成になっていて、「そろそろ梅の季節、今年は梅干しを仕込みたいな」とか「近所のキンモクセイはいつ咲くかな」などと楽しんでもらえたら嬉しいですね。

 鹿島の活動拠点で担当職員の上滝さんと一緒に。のどかな里山風景に癒されます。
鹿島の活動拠点で担当職員の上滝さんと一緒に。のどかな里山風景に癒されます。
日髙 関わってくださった人たちへの感謝がすごくあって。前提としてお仕事として関わっているんですけど、それだけじゃない関係性ができたように思います。しばらく行かなかったら「大丈夫?元気にしてる?」と連絡をくれたり、すごく温かく見守ってくれたり、心配してくれたり、気にかけてくれたり。そういった近しい親戚のおじさん、おばさん、お兄さん、お姉さんみたいな感じで気にかけていただける方がたくさんいてありがたいです。
私は祖父母と一緒に暮らしたことがなく、かつ一人っ子ということもあり、地域の方や年代の異なる方との関わり方がよく分からなかったんですけど、協力隊として色々な世代の方と触れ合う機会を通して、自分なりにしっくりくる感じが掴めてきました。この経験は今後も生かせると思っています。
やりたいことがあって佐賀は離れるんですけど、私にとって協力隊は楽しいことや学びしかなかったです。好きなことをやらせてもらえて、とても充実した3年間でした。感謝でいっぱいです。
3年間、思いっきり野山を駆け巡った日髙さんの笑顔からは、逞しささえ感じます。一番の財産だと話す、人との出会いをまとめたカレンダー。どんな仕上がりになるのか、とても楽しみです。
※この記事は2024年11月取材時点のものです。
取材・文 眞子紀子

追記
日髙さんは2025年2月末に任期を満了され、SML(佐賀県地域おこし協力隊)を卒業されました。任期中には佐賀県で2人目となる「山菜アドバイザー」の資格も取得され、卒業後はこの3年間で身につけた山野草の知識を糧に、奈良県の宿でお仕事をされるそうです。新たなフィールドでも野山を駆け回り、人と人、里と人をつなげる日髙さんの姿が目に浮かびます。また、佐賀にも遊びに来てくださいね!
日髙さん、3年間お疲れ様でした。